BLOGブログ
2024.02.16
デジタルサイネージのモニターに使うなら業務用とテレビどっちが最適?
 みなさんこんにちは、ビスコサイネージの渡辺です。
みなさんこんにちは、ビスコサイネージの渡辺です。
広告や情報を発信する媒体として様々な場所で見かけるようになったデジタルサイネージ。
そのモニターはコンテンツの訴求力に関わる大事な要素ですが、業務用のモニターと一般家庭用のテレビは見た目が似ているため、違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、業務用モニターと一般家庭用のテレビの違いについて解説していきますので、デジタルサイネージの導入を検討している方は参考にしてみてください。
デジタルサイネージについて
既にご存じの方も多いと思いますが、まず初めに「デジタルサイネージ」について簡単に説明していきます。デジタルサイネージとは、液晶やLEDモニターを使って静止画や動画、音声などのコンテンツを配信するメディアのことをいいます。
最近では、街中の大型ビジョンや商業施設、公共施設、交通機関、オフィス、病院など、屋内外問わず幅広い場所における広告・情報発信を行うツールとして活用されています。
デジタルサイネージは、表示するコンテンツを柔軟に変更できるというのが特徴で、モニターが設置されている場所や見られている時間帯、視聴者に合わせて自由にコンテンツを変更することが可能です。従来のアナログ看板ではできなかった「時」と「場所」に適応した情報発信が行える情報発信媒体として今後の活躍も期待されています。

業務用モニターとテレビの違い
様々な場所で活躍しているデジタルサイネージですが、機器を導入する際に知っておきたいのが業務用モニターと一般的なテレビモニターの違いです。一見すると同じように見えますが、性能面に違いがあるのでここではどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
1.耐久性
1つ目の違いとしてあげられるのが「耐久性」です。一般的なテレビは居住空間で使用することを想定して造られているため、業務用モニターに比べて耐久性が低いです。
例えば、連続稼働時間で見てみると、業務用モニターは24時間連続稼働させても故障しないように効率的に機械の熱を逃がす設計になっているものが多く、長時間でも安心して稼働させることが可能です。
一方、一般の家庭用テレビはここまで連続して稼働させることを想定した設計になっていないため、1日中電源をつけているとモニターが焼き付けを起こしたり、製品寿命を縮める要因となってしまいます。
また、屋外にモニターを設置する場合には、雨やホコリ、直射日光にさらされる過酷な環境下で稼働させることになるため、業務用のモニターには防水防塵性能が備わっており、画面も強化ガラスで覆われています。
一方、一般的なテレビは防水防塵性能が備わっておらず、画面もむき出しになっているので屋外で利用するのにはおすすめできません。
2.モニターの明るさ
2つ目の違いとしてあげられるのが「モニターの明るさ」です。デジタルサイネージは、ターゲットに情報をしっかり届けることが求められるため、コンテンツの見やすさが大切です。コンテンツの見やすさを追求するためにはデザインも考慮する必要がありますが、最も影響を及ぼすのがモニターの明るさです。
デジタルサイネージを使って情報発信する際には、屋内への設置で「350~1000cd/㎡」、屋外であれば「2500~5000cd/㎡」くらいの明るさが必要とされており、業務用のモニターはこのレベルの明るさを備えています。
また、業務用のモニターには、周辺環境に合わせてモニターの明るさを自動調整してくれる機能が搭載されているものもあるので、最適な状態を保ちながらコンテンツ配信を行うことができます。
一方、一般的なテレビの明るさは「350~500cd/㎡」となっており、屋内の明るい場所や屋外に設置をすると、周辺環境の明るさに負けてモニターに表示されているコンテンツが見えなくなってしまうため注意が必要です。
3.設置方法
3つ目の違いとしてあげられるのが「設置方法」です。業務用のモニターは、縦・横どちら向きでも設置が可能なので、設置場所や用途に合わせて自由に選択することが可能です。また、必要に応じて複数のモニターをつなげて1枚の大きなモニターとしてコンテンツを配信することもできます。
 一方、一般的なテレビは基本的に横向きでの設置しかできません。また、テレビ用モニターは画面の周りの黒い枠(ベゼル)の幅が広いので、複数台を連携させるといった使い方には向いていません。
一方、一般的なテレビは基本的に横向きでの設置しかできません。また、テレビ用モニターは画面の周りの黒い枠(ベゼル)の幅が広いので、複数台を連携させるといった使い方には向いていません。
4.コンテンツの再生方法
4つ目の違いとしてあげられるのが「コンテンツの再生方法」です。業務用モニターは、USBやSDカードを使ってコンテンツの配信を行いますが、機器に再生プレイヤー機能を搭載しているものも多くあるので、スケジュールを設定してコンテンツの配信を行うことが可能です。
一般的なテレビモニターもUSBなどを使ってコンテンツ再生が行えますが、再生プレイヤーを搭載しているものはなく、スケジュールを設定してコンテンツ配信を行うことはできません。

5.商品サイクルの違い
5つ目の違いとしてあげられるのが「商品サイクル」です。業務用モニターは、モデルごとの製造期間が長いため、故障しても部品の取り寄せや同じモデルへの買い替えが比較的容易にできます。
一方、一般的なテレビは商品サイクルが短く、使用しているモデルが数年で廃盤になってしまったということが起こりやすいです。その場合、故障した時に部品の取り寄せや同じモデルへの買い替えができないため注意が必要です。
業務用モニターとテレビモニターは見た目の違いがほとんどないため、価格が高い業務用モニターはコストパフォーマンスが悪いと思われがちですが、業務用モニターには一般のテレビにはない性能や機能、耐久性が備わっています。
そのため、情報発信を行うデジタルサイネージとして運用する場合は、業務用のモニターを利用するのがおすすめです。
しかし、運用方法や設置環境によってはテレビモニターを使用することもできるので、なるべく費用を抑えたいという方は、テレビモニターで効果検証しながら運用を始めてみるのもいいかもしれません。
どのように運用したいかをイメージし、必要な機能とコストのバランスを考えて検討するようにしましょう。
デジタルサイネージ導入に必要なもの
ここでは、業務用のモニターを利用する際に必要なものをご紹介していきます。・モニター
コンテンツを配信するディスプレイです。業務用のモニターには屋内用と屋外用のもの、そしてネットに接続するものとしないものがあるので、設置する場所や希望する運用に合ったものを選択するようにしましょう。
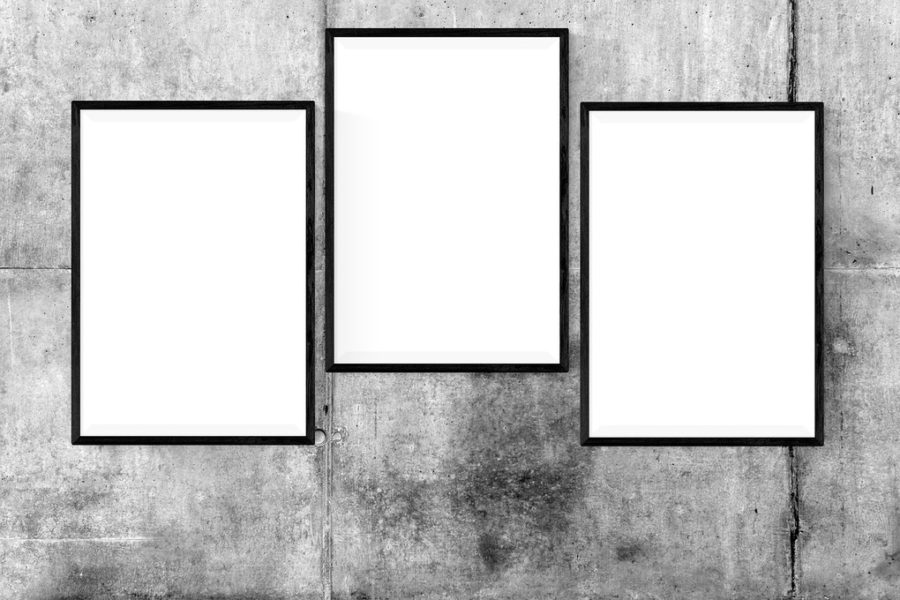
屋内用モニターと屋外用モニターの違いを詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひチェックしてみてください!
・CMS(コンテンツ配信管理システム)
ネット経由でコンテンツを配信する場合には、モニターに映すコンテンツや配信スケジュールの管理・設定を行うための「CMS」が必要です。
最近ではクラウド型の月額費用を支払って利用するサービスが主流となっています。システムによって機能や月額利用料が異なります。トライアルを実施しているサービスも多いので操作性を試して比較してみるのがおすすめです。
▼bisco CMS
弊社でもソフトウェアのインストールが不要で、モニターに繋ぐだけで簡単にコンテンツ管理・配信が行えるCMSをご提供しております。
30日間無料トライアルも実施しているので、導入をご検討中の方・操作性を試してみたい方はぜひ体験してみてください!

bisco CMS
・再生プレイヤー(STB)
ネット経由でコンテンツを配信する場合には、モニターにコンテンツを映す再生プレイヤーとなるSTBも必要です。
STBはコンテンツを再生する機能のみを搭載した機器で、ディスプレイに内蔵されているものと外付けタイプのものがあります。
まとめ
以上、今回は業務用のモニターと一般的なテレビの違いについてご紹介しました。見た目は似ていても業務用のモニターとテレビモニターには性能や機能、耐久性といった面でさまざまな違いがあるので、運用目的や設置環境などを考慮して最適な機器を導入するようにしましょう。
弊社では、お客様のご要望に合わせたデジタルサイネージ機器の導入サポートを実施しております。デジタルサイネージにご興味のある方、導入をご検討中の方はお気軽にご相談くださいませ!
お問い合わせはこちらからお願いいたします!
RELATED POST関連記事
BLOG&COLUMNブログ
屋外サイネージ
2024.07.26
屋外デジタルサイネージの防水防塵性能とIP規格について解説
屋内用デジタルサイネージにはない屋外用デジタルサイネージの特徴やIP規格の詳細、実際の運用における注意点についてご紹介します。ブログ
2024.07.18
インバウンド対策とは?効果を得るための具体的な対策事例もご紹介
訪日外国人数が増加している日本におけるインバウンドの現状と効果的なインバウンド対策の事例についてご紹介していきます。飲食店
2024.07.12
東京都の飲食店に上限300万円補助「インバウンド対応力強化支援金」とは?
飲食店関係者の方に向けて東京都と公益財団法人東京観光財団が実施している「インバウンド対応力強化支援補助金」についてご紹介していきます。









